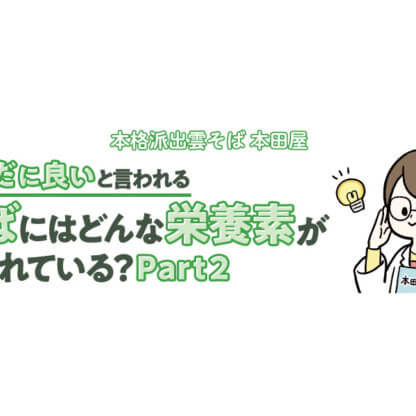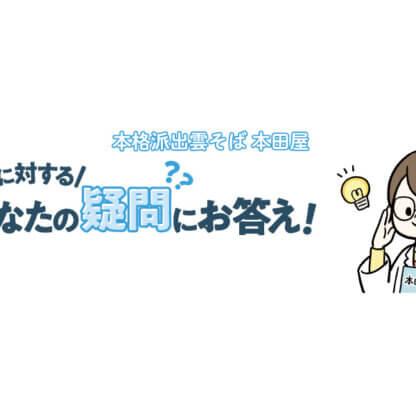出雲そばの定番「割子そば」とは?正しい食べ方を徹底解説

出雲の郷土料理「出雲そば」。
その出雲そばには食べ方が大きく2通りあります。
ひとつは、出雲そばの代名詞ともなる「割子(わりご)そば」。もうひとつは温かくして食べる「釜揚げそば」があります。
この記事では、「割子そば」の魅力を紹介します。
目次
出雲の伝統料理「割子そば」

割子そばは、島根県出雲地方の郷土料理「出雲そば」の食べ方の一つで、割子という朱色の丸い容器の中にそばを盛って食べていきます。
出雲そばと聞くと、この割子そばを思い浮かべる人が多いようです。
一般的には3段重ねで提供され、一段ずつ薬味やつゆを加えて、次の器に移して食べていくスタイル。
この独特な形になったのは、江戸時代までさかのぼります。
初期の割子は四角い重箱だったため、隅に食べかすが残りやすく衛生面での問題があったとされ、 明治時代以降、「洗いやすい」「衛生的である」として丸い漆器へと変わっていきました。
名称の由来~割子とは~

一説によれば、江戸時代の松江では野外でそばを味わう際に「割籠(わりかご)」と呼ばれる使い捨ての弁当容器が用いられており、その名残から「割子」と呼ばれるようになったといわれています。
別の説では、出雲地方では昔から重箱を「割盒(わりごう)」と呼んでいたことがあり、その呼称が転じて「割子」という名に定着したとも伝えられています。
「挽きぐるみ」のそば粉を使用する出雲そば

出雲そばならではの特徴のひとつが「製粉方法」にあります。
一般的なそば作りでは、そばの実から外殻を取り除いてから粉にしますが、出雲そばの場合は殻ごと丸ごと石臼で挽き込みます。
そのため色合いはやや黒みがかっているのが特徴。
殻も含めて粉にしていることで、香りや風味が一層力強く引き立ち、出雲そばならではの豊かで深い味わいを楽しめるのです。
出雲流・割子そばの食べ方手順
1.まずは一段目のそばにお好みで薬味をのせていきます。

2.上からつゆを回しかけ、1段目から食べていきます。
ポイント:つゆは器の中で「の」の字を描くように注ぐのがコツ。かけすぎないことで、そば本来の香りと風味を楽しめます。

3.一段目を食べ終えたら、残ったつゆを次の器へ移し、お好みでつゆと薬味を加えていただきます。(3段目も同様)
ポイント:段ごとに薬味を変えてみると、味わいのバリエーションが広がり、最後まで飽きずに楽しめます。

4.全て食べ終えたら、最後にそば湯とつゆを混ぜて飲むのもおすすめです。

お店ごとに異なる割子そばの種類

島根県内には数多くの出雲そば専門店があり、その多くで看板料理として「割子そば」が提供されています。
地元の人々はもちろん、観光で訪れる人々も注文する人気メニューです。
通常、割子そばは三段重ねが一人前とされていますが、五種類の味わいを楽しめる「五色割子そば」といった個性的なメニューや、割子そばに天ぷらを添えた割子そばもあります。
お店ごとに工夫された味わいやユニークなメニューが揃っているため、食べ比べなどをしてみるとより楽しさが増すでしょう。
ありそうで無かった、自宅でたのしむ「割子そばセット」

出雲そばの老舗「本田屋」では、自宅でも本場の味を楽しめるよう「割子そばセット」を販売しています。
セットには朱塗りの割子の器(三段)とつゆ差し、国内自給率わずか0.1%の島根県産のそば粉を使用した出雲そばがセットになった贅沢な逸品です。
本田屋のそば作りは、素材本来の良さを活かすために食品添加物などは一切使用せず、そば粉と小麦粉と食塩のみでお作りしています。
小さなお子さまからご年配の方まで、幅広い世代に安心して召し上がっていただけます。
こちらの商品は、ご自宅用ではもちろんのこと、ご贈答用にも喜ばれる商品です。
日頃の感謝を伝えるために、少し贅沢なそばを贈ってみてはいかがでしょうか。